![]()
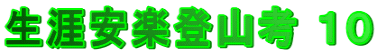
恥ずかしくても助けを呼ぼう
|
それにしてもH部氏は、よほど腹に据えかねるとみえて、当の岳人編集者という自らの立場を十分わきまえながらも、敢えて反論を掲載した。だが、それほどまでして反論するからには、もっとましな、多くの読者が納得できるような見解を述べてほしかった。これではまた新たな反論が寄せられるだろう。そうなったら編集部はどこまで深入りするつもりなのか。残念ながら、東京新聞の岳人は8月号で終わり、編集陣もがらりと入れ替わることだろう。するとこの問題は幕引きとなるかもしれない。 引き続き編集に携わることになっているH部氏は、私に反論する気があるなら新岳人に載せてやってもよいみたいなことを言ったらしいが、彼とはいくらやり合っても意見が合いそうにない。それで他の読者が反論してくれることを期待して、ひとまず静観しようと思う。代わりにこの場で書く。 |
H部氏が登山者として優れていることは認めるものの、その登山観には何十年も前の「エリート登山家」を思わせる臭いがある。山は生半可な考えで登るものではないという気持ちが強すぎると感じる。そこで想像するに、彼にとってはこんにちの「中高年登山ブーム」はきっと好ましいものではないのだろう。にぎやかに登る中高年登山者の群れは、彼の眼には軽佻浮薄で邪魔な素人集団と映るのかもしれない。 過度の「自己責任」論は人を山から遠ざけてしまう。「自分が悪いのだから救助を当てにしてはいけない。交通事故ならいつでも救急車が駆けつけるが、山の事故と交通事故は違うのだから、たやすく助けが来ると期待してはいけないよ」、ということだ。それ自体は正論だとしても、極論すれば、遭難のカタはみんな自分でつけろということになる。そうできるならよいが、できない人の方が圧倒的に多い。 |
|
◇誰かは遭難する 山の事故と交通事故が違うものかどうかは関係なく、事故は必ず起こる。そして事故を起こすのは未熟な登山者ばかりではない。これまで幾多の優秀な登山家が山で命を落とした。それは間違いなくこれからも続く。速やかに救助されていれば死なずに済んだケースも少なくないことだろう。救助を要請するのは恥だという意識から、落とさずに済んだはずの命を落とした人だっているかもしれない。 山の事故救助の場合、手間暇の度合い、困難さ、危険さのどれをとっても交通事故の比ではないが、だからといって両者の救助体制に優劣があってよいということにはならないと思う。なれどH部氏の考えを推し進めれば、違いがあって当然ということになりはしまいか。なにせ「何かあったら助けてもらえばいい」と考えるのは「社会に対する甘え」なのだから。そんな考え方をする奴は山へ行くなということになっては大変だ。もちろん私だって、はなから救助を当てにする考えを好ましいと思うはずはない。 |
ともかく、私が一番言いたいのは、「何かあったら助けてもらえばいい」というのではなく、山で必ず誰かは遭難するのだから、もし自分が遭難して自力下山が不可能な事態になったなら、ためらわずヘリコプターを呼べばよいということだ。それでも、まだおかしいと言う人がいるなら、私の真意を理解してくれなくてよい。そんな奴はヘリを呼ぶな!! ◇新しい岳人はどうなる H部氏は新しい岳人の編集部に残るということだ。なにやら新岳人の輪郭が垣間見えるような気がする。もし、H部氏の価値観が新岳人の基本スタンスであるとするならば、少なからぬ読者が離れていくのではなかろうか。私も積極的に買おうとは思わない。 ともあれ、変わっていくのは悪いことではないし、モンベルの情報誌・広報誌のようなものになる恐れがあるとまでは思わないものの、その行く末にはいくばくかの不安を覚えている。 |
 |
| ◇救助体制が整った健全な社会 以下は上記とは直接関係ないもの、一般論として述べる。山では何かあったら助けてもらえばよいという態度が、「社会に対する甘え」であるかどうかは別にして、社会では何かあったら助けてもらうのは極めて自然なことだ。火事になれば消防車に来てもらう。急病になれば救急車で病院へ運んでもらう。犬や猫でも川で流されれば警察官や消防隊員が駆けつける。人は皆、そういう事態になったら当然のごとく助けてもらえると信じている。それが健全な社会だと思う。 なんの備えもせずに安易に救助を期待するのはよいことではないが、そういうのは登山者に限ったことではないだろう。そんな負の面があるのは、様々な人格の人間が存在するこの世の現実問題として避けられないことだ。ともあれ、何かあれば助けてもらえるという前提があるから、人は安心して生きていけるのだ。 |
◇交通事故と山の事故 私なんぞ、山へ行くときは登山中の事故よりむしろ行き帰りの交通事故の方を心配する。高速道路を利用する場合はなおさらだ。ことほどさように、高速道路を通るのは怖い。そこで交通事故死と山の遭難死を比較することを思い立った。この際、少数含まれる外国人のことは無視して考える。 私はこれまでも、日本人全体のうち交通事故で死ぬ人の割合と、登山者全体のうち山で死ぬ人の割合はさほど変わらないのではないかと想像していた。調べてみると、交通事故での死者は1970年には16000人以上いたが、去年まで13年連続で減少が続き、ここ数年は4500人程度。一方、山の遭難死は逆に増加傾向にあり、最近は年間280人程度。昨年は一気に増えて320人で、過去最高とのこと。 |
| ◇確率は変わらない? 1億2千7百万人のうち4500人が交通事故で死ぬ。その割合でいくと、約790万人につき280人という計算になる。790万人というと登山者の数とそう変わらないように思える。正確な登山者数なんぞわかるはずもないし、登山者の定義もあやふやなものだが、登山人口900万人と言われた時期もあると記憶する。7月15日朝のNHKニュースでは860万人と言っていた。だとすると、国民全体のうち交通事故で死ぬ人の割合と、登山者のうち山で死ぬ人の割合はほとんど同じか、むしろ交通事故死の方が高いかもしれないということだ。 一般的には、交通事故より山で死ぬ方がずっと多いという印象があるが、死ぬ確率という点では両者そう変わらない。つまり交通上の危険も多いのだ。 遭難が多発する山とほとんど遭難が起こらない山があるから、一口に登山者といっても登り方のスタイルによってそれぞれ死ぬ確率は大きく異なるという理屈は成り立つが、それは交通事故でも同じこと、人間死ぬときはどんなところでも死ぬ。 H部氏は山岳遭難と交通事故は「リスクを容認しているかいないかという点で大きく異なって」おり、「同列に扱うことは意味をな」さないと言うが、人は山がとても危険だと認識していても、交通事故では山のような危険性は認識していないという意味ならば、それは容認していないのでなく、リスクに気がついていないだけのことだ。つまるところ、そんなことを言うのは交通事故より山の方が危ないに決まっているというH部氏の思い込みのなせるわざだ。 |
◇登山者も国民の一人 もはや取り立てて特別な存在でない登山者、国民のだれもが登山者となりうる状況だ。病気になったら救急車を呼べばよいというのが一般国民の意識であるなら、遭難したら助けてもらえばよいという考えが、一般国民の一員たる登山者の意識であって不思議はない。 タクシー代わりに救急車を利用する人がいれば、特に急を要するわけでもないのにヘリコプターを呼ぶ登山者もいるだろう。どちらも好ましいことでないのは言うまでもないが、それがありふれた実態というわけではない。多くの場合は本当に困ったからなのだ。遭難救助を期待することを、いつまでも社会に対する登山者の甘えと言っている時代ではないのかもしれない。  |
| ◇行間を読むことの難しさ 有名な俳句の「雀の子 そこのけ そこのけ お馬が通る」は、早くどかないと危ないよ、という雀に対する愛情をうたったものと解するのが普通だ。わずか17語の中に、そこに込められた作者の心情を深く読み取って(想像し推察して)そのような解釈になるわけだ。 しかしながら意地悪く考えれば、馬が通るのに邪魔だから早くどけという意味にとらえることもできる。もしこの句が名もなき人の作だったとしたなら、必ずしも雀への愛情という解釈は確立しなかったかもしれない。一茶の作風を考えれば雀への愛情説が有力になるのだが、作風のわからない無名の人の句なら、愛情を表したものと考える人ばかりではないだろう。 |
6月号の文章も、いうなれば後者の場合のように、非好意的に理解されたわけだ。要するに、字面だけではいろんな解釈がありうるということだ。まして、憲法でさえいいように解釈される時世なのだから。何を言いたいのかを正確に書き表すのと、何を言っているのかを正確に理解するのとは、いずれ劣らぬ至難の業だ。 良いたとえではないが、「舌足らず」があれば、「口が滑る」こともある。後者の場合、はからずも本音を暴露してしまうことがあれば、もののはずみで真意とはまるで別のことを言ってしまうこともある。 私も気を付けて書いているつもりが、誤解されることがしばしばある。「口はわざわいの元」とはよく言ったものだ。 |
| 補遺 もし遭難したらどうするかという前提で話を進めているのに、その前提を無視して勝手な想像をする人がいた。その人は、もし遭難したなら、この際恥やメンツは捨てて救助を呼ぼうとこちらが言ったことに対して、「何かあったら助けてもらえばいい」、「助けられることを恥だと思わなくていい」と言っていると解釈する。 |
そんな風に読まれることもあると心しておかねばならぬと思う。それはそうと、書物の編集者という人たちは、内容をきちんと読み取ったうえで行間まで読んで、筆者が本当に言いたいことは何かを理解するものだと思っていたけれど、そういう人ばかりでもないようだ。 |