![]()
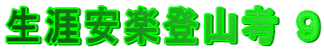
遭難と恥の意識
|
◇予期せぬ連載中止 格式と伝統ある雑誌「岳人」が8月号限りで東京新聞の手を離れ、モンベル系列の軍門に下った。そのため、連載「生涯安楽登山考」は8月号で打ち切りになった。1年間連載ということだったのに、新発行元はそれを反故にした。のみならず、そのことに対して今もって何の挨拶もないのだから失礼千万な話だ。 既に1年分の準備はできていたので、筆者了承のもとこの場を借りて続きを発表することにした。して、新しい発表スタイルは当初の構想になかったことから始まる。それというのも、次の事情による。 |
◇予期せぬ形の反論 6月号の「生涯安楽登山考」に対して8月号のかわら版ページに批判文が載った。それも、岳人の編集部員が岳人に書かれた論考について岳人上で反論するという、「そんなん、ありかー」と言いたくなるような、まるで背後から鉄砲を撃たれたような気分になるものだった。以下にその文章を全文紹介する。但し実名は伏せる。 |
| ◇登山の自由は社会的信用から H部B祥 一冊の「岳人」を作るのにすべての原稿を全スタッフが精読するわけではありません。6月号に掲載した「遭難救助とヘリコプター」(正しくは遭難事故とヘリコプター:筆者注)に関する記事を目にしたのは編集の最終段階でした。軽く読んで違和感を感じたのですが、時間的な問題でその違和感は誌面に反映されることはなく、発売されました。 |
登山とは人間の生活圏から離れて、自然環境の中で山に登って帰ってくる行為です。街より危険や困難が多く、命を失ったり、大きなケガをするリスクも高くなります。そのような危ないところを登るという文化が、社会的に許されているのはなぜなのでしょうか。 時に命懸けの行為になるとわかっていても、それが許されるのは登山者が自力下山という覚悟をもって山に入るからです。自分の力で戻っているという「自己責任」を前提としているから、登山者は自分の自由意思で山に入ることができるのです。 仮にその前提がないなら、登山者は山に入る自由を奪われても仕方がありません。もし「何かあったら助けてもらえばいい」と考えているなら、それは社会に対する甘えです。「迷惑なので山に入らないでください」と社会から登山を規制されても仕方がないわけです。 |
| だからこそ登山者は、できる限り自分で下山する努力を続けなくてはなりません。自力下山は自分の登山を自分で締めくくるという、登山者のすべてが持つべき意思の延長であり、登山者が登山の自由を守るための行為でもあります。 生死にかかわる場合に、現実問題としてヘリコプターに救助要請するのが社会常識に反しないとしても、「助けられることを恥だと思わなくていい」と登山者が発言することは、登山者の社会的信用を失うことにつながります。 登山は自由であり、登山観もそれぞれだと思います。ただ、登山の信用を失いかねない意見を「岳人」が教育的な項目内に掲載することは、自分たちが乗っている土台を自らで壊すことになりかねないと私は考えます。そのため聞き苦しい内部批判であることを承知で、意見を述べました。 |
発行母体が変わっても、リスクと遭難と救助に関しては登山者が真摯に考えていくべき問題だと思います。もし、意見がありましたら、私の裁量の及ぶ範囲で対応させていただきますので、多くの意見を新生「岳人」にお寄せいただけると幸いです。 [補遺] |
 |
| 事前に別の編集部員から、上記の反論が出るという連絡があったので、当人に読んでもらうために一文をしたためた。次に紹介するのがそれで、反論というよりは弁明に近いものだ。 ◇「登山の自由は社会的信用から」への感想 ご意見をいただいて、いろいろ考えさせられ、反省もしております。 一人の見解に対して反論があるのは当然です。ただ、紙数の限られた中で文章化するとなると、時として本人の意図したものと違った意味合いに受け止められてしまう書き方になることがあります。また、書き手が正しく伝えることができ、読み手が正しく理解したとしても、賛同が得られるかどうかは別問題です。 私個人としては、遭難するのは恥ずかしいことだと思っています。不名誉なことです。もし自分が遭難して救助隊等に助けられたなら、救助隊の方々には心より感謝するとともに、救助隊だけでなく「世間様」に対して大変申し訳なく思うことでしょう。一方、現実に安易に救助要請する人がいることも知っています。 私はこれまで何度か岳人誌に執筆する機会を与えていただきましたけれども、もし私に遭難して助けられた過去があったなら、私は決して書くことはなかったでしょう。それは、私自身に「遭難した者がエラソーなことゆうな」みたいな気持ちがあるからです。 |
ただ、これまでの連載を読んでいただければ、私が念頭に置いている対象は主として普通の登山愛好者であることをわかっていただけるでしょう。そのような人たちに、もし自力下山が不可能ならば、あまり恥ずかしいと思わずにヘリコプターを呼ぶことを躊躇しなくてよいと言いたかったのです。たしかに山でも車でも事故を起こすのは恥ずかしいことで、できるだけ隠したいという気持ちは誰しも持っていると思います。でも、この際そんなことを言っている場合ではないと私は言いたかったわけです。「何かあったら助けてもらえばいい」よ、と言っているつもりはありません。ですが、そのような風潮を助長する書き方だといわれれば、そうかもしれません。筆力不足のため、そのあたりをうまく伝えることができませんでした。 それでも同じ号で、セルフレスキューについて少しは勉強するほうがよいことなどを述べています。ほかの号でも、山の危険性について何度も触れたつもりですし、なんの対策も取らずに遭難したら助けてもらえばよいと考えて構わない、などとは一度も言っておりません。 私なんかよりはるかに実績のあるH部氏ら「登山家」と呼ばれる人が、「自力下山」という覚悟をもって、決して人様の世話にはならないという強い気持ちで山に行くのは、それはその人の哲学として否定しません。 |
| しかしながら、多数を占める登山愛好者にもそれを求めるとするなら、ひいてはその人たちを山から排斥することにつながりかねないと思います。こんにち多くの国民の生きがいや楽しみとなっている登山が、一部の人の「修行」のようなちょっと手の届かないものと化してしまうのではありませんか。H部氏はこんなつもりではないでしょうが、私には「そのような心構えのない者には山に登る資格がない」と言っているように読めてしまいます。 (補遺)の、山岳遭難と交通事故を「同列に扱うことは意味をなしません」とは、どういう意味か理解しかねます。 |
このように、文章では真意を伝えきれないことや、意図したとおりに理解してもらえないことがありうるのは避けられません。もちろん、考えそのものがおかしいこともあるでしょう。さらには、「同じ人間は同じことしか言えない」というのが私の持論です。発想パターンが決まっています。一人の意見は一面的な見方であったり、思い込みから抜けきれなかったりします。だからこそ、互いに意見をぶつけ合う討論や、非難の応酬ではない生産的な相互批判が必要だと考えます。H部氏のご指摘もそのようなものとして、ありがたく頂戴いたします。 |
| ここまでの文章はH部氏に読んでもらうために書いたのだから、相当やんわりと表現したつもりだ。ここからはもう少しストレートに書くとしよう。 H部氏が私の「感想」を読めば少しは考えを変えてくれるかもしれないと思っていたが、氏の反論は1、2ヶ所の脱字訂正等を除き原文通り掲載された。氏の強い意思がうかがえる。 ◇伝えられなかった真意 H部氏は、私の意見を「登山の信用を失いかねない意見」と評している。なるほど、この号しか読まなければそのように受け止める人が他にもいるだろうことは認める。それは申し訳ないことだ。 |
「自力救助(セルフレスキュー)が困難だとわかったら、すんなり救助要請をするのが賢明というもの。SOS発信は恥だなどと思わず、また遭難呼ばわりされるのは嫌だという意地や誇り、メンツなどはこの際、潔く捨てよう」、「交通事故で救急車に乗ることに抵抗はなくても、山の事故だとヘリコプターどころか、担架に乗ることさえ拒否する。そんな考えはもう捨ててもよいのではなかろうか」という表現、そして写真の説明「救助要請は恥ずかしいことではない」、さらに「そのプライド、やせ我慢は愚」という冒頭部分の見出しなどが特にそういう印象を与えたものと思う。 |